はじめに
「人工授精を繰り返しているけれど結果が出ない」「注射や副作用がつらい」――そんな方は、次のステップとして体外受精を考える場面に直面することがあると思います。
私自身もタイミング法や人工授精を数回経験しましたが、そのたびに**OHSS(卵巣過剰刺激症候群)**を発症してしまい、「このまま毎月AIHを繰り返すのは身体的にも精神的にもきつい」と感じていました。
そこで転院を機に、体外受精(顕微授精)に進むことを決めました。
この記事では、「カウフマン療法から採卵まで」 の流れを、私の体験をまじえて詳しく書いていきます。これから体外受精を考えている方の参考になれば嬉しいです。
私が体外受精を選んだ理由
体外受精を決意した大きな理由は3つあります。
- OHSSのリスクを減らしたかった
人工授精では毎回注射によってOHSSを起こしていました。体外受精なら一度の採卵で卵子を複数確保でき、毎月注射を繰り返す必要がなくなります。転院前の先生からも体外受精を考えた方がよいと助言もいただいていました。 - 妊娠率の違い
AIHは1回あたりの妊娠率が約10%。一方で体外受精は、私の年齢では1回で約50%の確率と言われました。効率を考えても、体外受精の方が希望が持てました。 - 原因不明不妊の可視化
私は原因不明不妊でした。体外受精なら受精の段階や培養の様子から「どこに問題があるか」が見えやすくなるとおもいました。
体外受精とは卵子と精子を体外で受精させ受精卵を子宮に戻す方法です。
全体のスケジュール(私の場合)
実際に私が体験した大まかな流れは以下の通りです。
- カウフマン療法(約1か月)
- 卵巣刺激(自己注射や内服)
- 採卵
- 受精培養(最終的には顕微授精でした)
- 移植
- 判定
今回はこの中から、**1〜3(カウフマン療法から採卵まで)**について詳しく書きます。
カウフマン療法とは?なぜ必要なのか
転院後、まずは先生から「カウフマン療法をしましょう」と説明を受けました。
- 採卵に向けてまずは卵巣を休ませてリセットする
- ホルモンバランスを整える
- 次の卵巣刺激をスムーズに行えるようにする
服用するのは エストラジオール(卵胞ホルモン)とルトラール(黄体ホルモン)。
私の場合は19日間服用し、その後生理がきました。
「早く妊娠したい」と思っている私にとって、この期間がとても長く感じました。
転院が5月で、最短の移植は7月中旬。頭では必要な準備と分かっていても、「もう1日も無駄にしたくない」という焦りとの戦いでした。
通院スケジュール
- 初診(カウフマン療法開始)
- 卵巣刺激開始日(ホルモン値チェック)
- 採卵日を決める超音波検査
- 採卵当日
採卵までの通院は4回程度と少なめでした。AIHのときは排卵日時期は毎日のように注射で通院していたので、それに比べるとかなり楽に感じました。
自己注射を選んだ理由
採卵に向けて排卵誘発剤の注射が必要でしたが、病院に通うか自己注射かを選べました。私は仕事との両立を考えて自己注射を選択。自己注射は自分でおなかに注射を打たないといけないです。
はじめは注射が怖くて仕方ありませんでした。私は採血のときも針を直視できないタイプです。
ただ思っていた以上に注射針が細く痛くなかったため頑張れました。 刺激開始日病院で注射を一回、その後自宅で3,4回程自己注射しました。
自己注射ができるようになったことで「私、成長してる!」と前向きになれたのは意外な副産物でした(笑)。
薬や注射のタイミングはとてもシビアです。特に点鼻薬は時間指定があり、「間違えたら採卵ができないかも」とプレッシャーもありました。
私はスマホのアラームを細かく設定して、飲み忘れや打ち忘れを防ぎました。
採卵当日の体験
当日の流れ
- 朝一で病院へ
- 静脈麻酔で採卵
- 麻酔が効いて一瞬で眠る
- 気づいたらベッドの上で終了
初めての静脈麻酔はドキドキしましたが、痛みはほぼゼロ。
一瞬目が覚めた記憶はありましたが、すぐにまた眠らされて無事に終了しました。
採卵後の過ごし方
手術後はしばらくベッドで安静に。
水分や栄養補給のためにゼリー飲料を持参していて助かりました。
「採卵はすごく痛い」と聞いていたので構えていましたが、私の場合は静脈麻酔だったためほとんど痛みがなく、午後から在宅で仕事をすることもできました。
まとめ
AIHから体外受精に進み、まずはカウフマン療法〜採卵を経験しました。
- カウフマン療法で卵巣をリセット
- 自己注射で卵巣刺激(思ったより痛くない!)
- 採卵は静脈麻酔でスムーズに終了
準備期間は長く感じましたが、確実に次のステップに進んでいる実感がありました。
次回の記事では、「受精培養から移植までの流れ」 をまとめたいと思います。

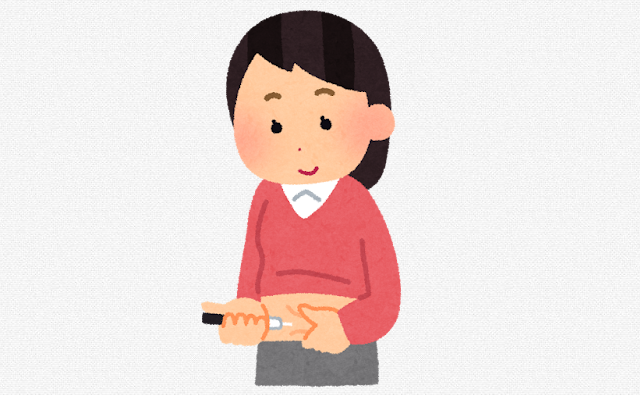
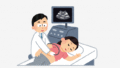
コメント